

目覚まし時計用アラーム4つ
ローリングストーンズのCan't Get no Satisfaction、木琴バージョン。いつも思うのだが、この二重否定の用法は厳密にはあやまりではないのか? もともと、空耳的に日本人の耳に聞こえたままを歌詞にするというコンセプトで「日本語」の歌にしようと試みたのだが、失敗...


タイで一番有名な幽霊の話
タイで一番有名な幽霊メーナーク。これまで何度となくドラマ化、映画化された女のオバケである。私の住んでいる運河沿いにマハーブット寺というお寺があり、境内の祠にこの幽霊が祀られている。 メーとはタイ語で母親のこと。ナークが名前であが、一種の信仰の対象として敬称的に「母なるナー...


マティチョン誌から(20170728-0803号)
今週は、国王誕生日があったため、表紙は現国王陛下の写真。従って、表紙に見出しはない。 巻頭言は、開始後3年たったデジタル放送について。ニュースに参入した各社が軒並み赤字を出していることを具体的な数字を示して伝えている。 ...


今週の一枚 祠猫(ほこらねこ) 20170730
夜、カミさんと一緒に近くのお粥屋で飯を食って帰ってくると、アパートの土地神様の祠に猫がいた。とっさに祠猫(ほこらねこ)と名付ける。 後ろを向いて毛づくろいしているところに近づいて、ミャーオと呼びかけたら、こちらを向いてくれた。こういう時、野良猫は逃げるものだが、奇妙な猫で、...


マティチョンの見出しから(20170714-20号)
下の大きな見出しは、 「トランプ、プラユットにご執心?」 2014年、軍が権力を掌握した時、当時のオバマ政権はクーデターを非難し350万ドル相当の軍事支援を停止した。国務省の人身売買リポートでも、「状況の改善に積極的な努力をしていない国」としてタイのランクを一つ下げてい...


演歌「闘う中卒」 訳詞
イサーン(タイ東北部)出身の演歌歌手マイ・ピロンポーンの「闘う中卒」。カミさんがファンなので昔からよく聞いていた。労働者を応援する日向的なルークトゥンを歌う人。 歌詞に出てくる「ラムカムヘン大学」は、バンコクにあるオープン大学で、誰でも入学はできるし、夜間や通信制の学部もあ...


タイ演歌「板切れと船」 訳詞
これもひと昔前に流行ったタイ演歌「板切れと船」。なんか、タイ懐メロ特集みたいになってきたが、以前、タイ語の勉強のために訳したものを、ここに保存しておこうという意図でして・・・。 「あなたの幸せのために私は身を引きます」という演歌の基本形ですな、この歌は。こういう男女関係にま...


バード・トンチャイの「直してあげる」 訳詞
タイの国民的歌手バード・トンチャイのソームダーイ(邦題「直してあげる」今、私がつけました)。ルークトゥーン歌手のチンダラー・ブーンラープとの共演したモーラムバージョンがお気に入りだが、これはバードが一人で歌っている。グラミーの公式サイトから。...
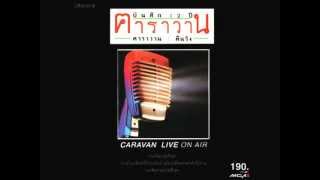
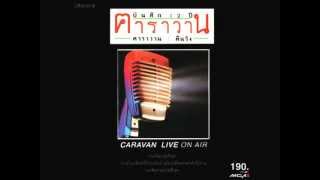
カラワンの満月 訳詞
カラワンの「満月」(故郷を思う) 学生運動の闘士だったガ-・カラワンが、弾圧を避けて森に逃れていた頃、同志が作った詩に曲をつけた。そういう政治的背景に全く興味はないが、良い歌ですな、これは。カラバオバージョンの方が歌はうまいが、完全に商売だから、彼らの場合。やはり、ちょっと...


プンプアンの「田舎歌手」 訳詞
タイ演歌の女王プンプアンの「田舎歌手」を、The Voice Thailand で決勝まで残ったテンモ-・ワンリカーが歌っている。 なんというか、すごく素直な、可愛いらしい歌詞ですな。以下、私訳。 田舎歌手 日は落ちかけ、たそがれ時、カラスもねぐらに帰るころ ...


カラワンの「花」 訳詞
カラワンの「花」。これ元歌は、喜納昌吉の「花」なんですが、タイ語の歌詞はちょっとイメージが違いますね。タイ語の歌詞の方が格調が高い。だから私訳。間違ってたら失礼。 題 あなたに花を届けよう この庭の花を全ての人に届けよう 近くにいる人にも、地平線の彼方にいる人にも...


A Journey to Buddha (TV Documentary)
The series of TV documentaries was produced a decade ago to celebrate Buddhist year 2550 and, in my opinion, remains to be the most...


「タイ人はどこから来たか?」(マティチョン出版)
「タイ人はどこから来たか?」 スチット・ウォンテート (マティチョン出版) 図解や写真が多くて楽しい本だが、結局のところ何を言いたいのか、よくわからない本でもある。 石器時代から現在のタイに様々な民族が住んでいたということは、タイ人が中国方面からこの地域に南下してきた新参の...









